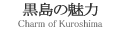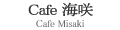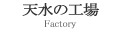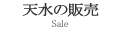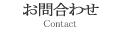佐世保の九十九島に浮かぶ水の島 黒島
黒島は佐世保北九十九島にある有人島の一つです。周囲約12km、面積5.3平方km。
黒島全域が国の重要文化的景観として保護されています。
島の8割がカトリック信者ですが、お寺もあります。
島にはバスもタクシーもありません。ゆっくり歩いて回るのも魅力の一つです。
島は意外とアップダウンがありますが、気持ちの良い風と美味しい空気をたっぷり味わってください。
黒島の魅力と見どころ
黒島天主堂(クロシマテンシュドウ)
黒島天主堂は明治33年、フランスのマルマン神父によってお建築されました。
黒島天主堂は、島の中心に当たる名切地区にあります。正面は北東を向いており、小高い山に囲まれています。ロマネスク様式を基調とする外観、正面中央にある鐘塔があり、木造及びレンガ造りで屋根は瓦、奥行き35m、間口15mの三廊式の教会です。
この三廊式は、長崎の大浦天主堂ととてもよく似ています。
内部にある12本の列柱は、円形の黒島の御影石で作った台座に16本の半円形の柱を付けた束ね柱と呼ばれるものです。ちなみに釘は使っていません。
天井は円形アーチを基調とした四分割リブ・ヴォールト天井。リブや天井の木目は刷毛で描かれたもので、櫛目引きと呼ばれる技法です。この方法はいくつかの教会堂や他の明治建築の扉などにも見ることができるため、当時としてはポピュラーな技法だったようです。
内部立体構成は下層よりアーケード・トリフォリウム・クリアストリーの三層構成でできています。とくにトリフォリウムには奥行きをもち、同じような造りの教会では、平戸の今村教会と平戸教会にしか見られません。祭壇部分は珍しい半円形の平面で有田焼のタイルを敷き詰めるなどの地方ならではの特徴が見られます。
黒島天主堂はマルマン神父という建築の技術が優れた外国人宣教師の強い指導の下で建築された地方教会堂で、学術研究によって長崎県下はもとより近隣の地域で後世建てられた教会建築に与えた影響はとても大きいことは明らかです。
ですから日本を代表する明治期に建てられた三層構成の教会群のひとつとして貴重な天主堂ということになりますね。
「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」としてユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載されましたが、残念ながら世界遺産への推薦は見送りになってしまいました。
世界遺産への登録が決まれば、たくさんの観光客の皆さんが黒島へ足を運ぶことになるでしょう。

信仰復活の地(旧出口邸跡・石碑)
日数にある信仰復活の地は代々カトリックの洗礼を受ける「水方」を務めていた出口邸があった場所です。
1865年 長崎の大浦天主堂では信徒発見という事件が起きました。それを聞いた出口大吉は「黒島にも潜伏キリシタンたちがいます。」と長崎まで告白に行くのですが、「残念ながら文言が間違っている。これまでの洗礼は無効。」と言われてしまうのです。
そこで大吉は度々長崎に出向いて教理を学ぶこととなります。
テストをパスし、ようやく受洗できた大吉は黒島に帰って600人に洗礼を授けました。
それ以外にも紐差、宝亀、生月などにも出向いてキリシタンの信仰復活を呼びかけて宣教して回ったのです。
そのため彼の洗礼台帳には「平戸の使徒」(使徒とはイエスの弟子に使われる言葉)と書かれています。
この石碑はシャトロン宣教師が黒島に訪れ、出口邸で初めてミサ聖祭を行った記念として1956年に作られました。
黒島の花崗岩自然石に「信仰発祥之地」と掘っていましたが、平成元年に文字のところだけ「信仰復活之地」と買えられました。
潜伏して信仰を守り続けていたので「復活」という語を用いることになったのです。
当時の潜伏キリシタン達ですが、まだ寺の檀家扱いで神様や仏壇を家においていました。
ですが長崎の宣教師に拒絶避難されてしまいます。そこで勇気を振り絞って神仏のすべてを焼き払い「これからはただゼウスだけを拝む」と意思表明し、カトリックへの復活を果たした事になります。
一部、洗礼が有効とされた平戸などの地域ではカトリックに復活せずそのまま隠れキリシタンといいう宗教的には違う分野になったところもあります。
それを思うと、黒島全信徒のカトリック復活はかなり奇跡に近いですよね
根谷アコウの巨木
アコウはサザンカと並ぶ黒島の代表的な植物です。アコウはクワ科に属し暖地に生える常緑高木で幹から気根を出して大きくなります。果実はイチジクに似ていて熟すと食べられるそうです。
黒島にあるアコウは屋敷林として植えられたと考えられています。島にある大きいものでは根谷の大アコウが有名ですが、この木は気根が幹の中程からたくさん垂れ下がっているのが特徴です。これは道路拡張の時に根のまわりが傷つきその回復のためだと考えられています。
あと名切の浜に下りる谷筋にも大きな岩を抱え込むように気根を張るもの、蕨にも同じく石垣を抱え込むように伸びている気根のアコウがあります。まるで石垣を根強くしているようにも見えます。比較的成長の早いアコウは会場からの強風対策でもあったようです。
黒島のふくれ饅頭
黒島のふくれ饅頭は、黒島豆腐と並びお祝いなどがあると必ず作られる家庭料理です。
小麦粉で作った生地で小豆あんを包み、「カッカラ」と呼ばれる葉っぱにのせて蒸し上げます。それをかまどに薪を入れ、せいろで蒸すのです。
各家庭でいろいろバリエーションはありますが、この葉っぱにのせるのは共通になります。
昔ながらのお母さんの味です。
「カッカラ」は「サンキラ」が訛ったものだと考えられています。葉っぱの形状から「サツマサンキライ」だと思われ、西日本では同じようにこの葉っぱにのせる、または包むという団子やおもあちが知られています。しかし、ほとんどが米を生地に使うもので小麦粉を使う例は少ないようです。
黒島では昔、島全体が金色に輝くくらい麦を育てていたという話を聞いたことがあります。
なので、きっと米よりも小麦の方がてに入りやすかったのでしょう。
くろしまっぷ
みずやでは、黒島の魅力を伝えるために「くろしまっぷ」を作成しております。
くろしまっぷの画像をクリックするとPDFデータがダウンロード出来ます。
店 舗

有限会社 みずや 黒島工場
Cafe 海咲(みさき)
〒857-3271
佐世保市黒島町4160-9
TEL :0956-56-2310
営業時間
10:30~16:00
定休日
毎週木曜日